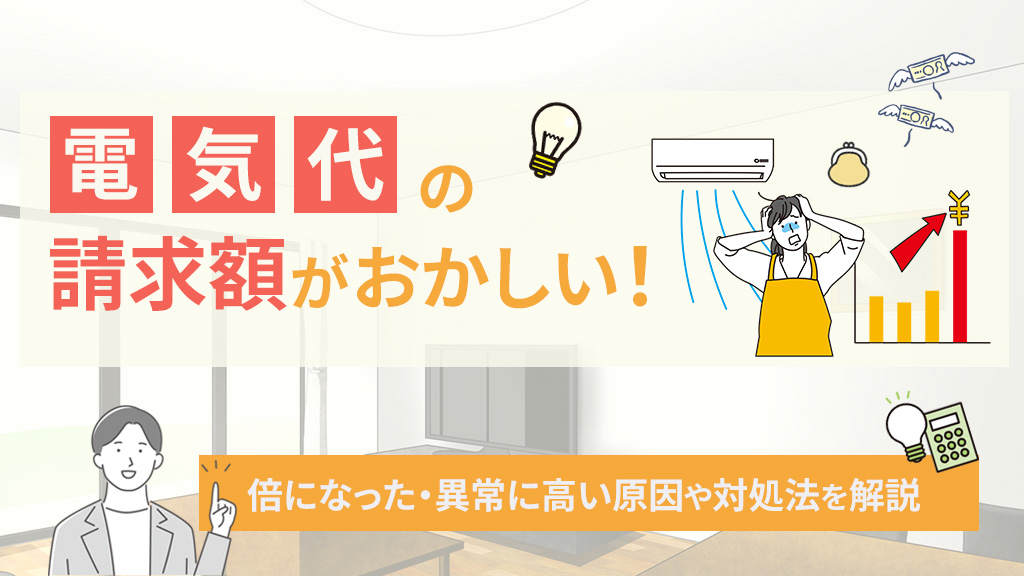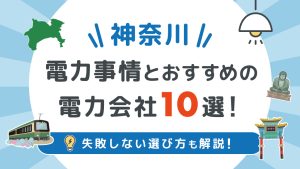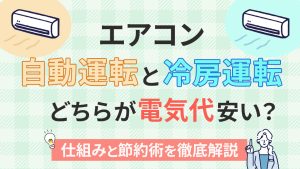「今月の電気代、なんだかおかしい…」「なぜこんなに高いの?」と、請求を見て驚いたことはありませんか?
急に請求額が跳ね上がっていると「おかしいのでは?」と不安になりますよね。突然電気代が跳ね上がっていると、不安になるのは当然です。
この記事では、電気代の請求がおかしいと感じたときに確認すべきポイント、電気代が高くなる主な原因、具体的な節約方法まで、詳しく解説します。
ご家庭の状況に合わせて、無理なく実践できる対策を一緒に探していきましょう。
- 電気代の請求がおかしいときの確認方法
- 電気代が高くなる主な原因
- 世帯別の平均電気代との比較
- 今日から始められる電気代節約術
目次
電気代の請求がおかしいときにまず確認すること

電気代の請求額に違和感を覚えたら、まずは基本的な確認を行いましょう。
電気代が高額になる理由は様々で、請求ミスではなく正当な理由があるケースも多いです。
以下のポイントを順番にチェックして、原因を特定しましょう。
検針票やWeb明細で使用量と料金単価をチェック
電気代の請求がおかしいと感じたら、まず検針票やWeb明細を詳しく確認しましょう。
検針票には、使用量(kWh)・料金単価・基本料金・燃料費調整額・再エネ賦課金などが記載されています。これらの項目を一つずつチェックすることで、どの部分が高額になっているのかを把握できます。
- 今月の使用量(kWh)が前月と比べて大幅に増えていないか
- 料金単価が変更されていないか
- 燃料費調整額が大幅に上昇していないか
- 契約アンペア数や基本料金に変更がないか
電力会社によっては、Webサイトやアプリで過去の使用量や料金を確認できるサービスもあります。
前年の同月と比較して使用量が増えているか確認
電気代を比較するときは、前月の請求額ではなく「前年の同じ月」と比べることが重要です。電気の使用量は、冷暖房を多用する夏(7月〜9月)と冬(12月〜2月)に大きく増加する季節変動があるためです。
今年の1月と去年の1月を比較して使用量が増えているなら、生活スタイルの変化・在宅時間の増加・新しい家電の導入などが原因である可能性が高いでしょう。
もし、前年同月と比べて使用量が明らかに増加しているにもかかわらず、生活に大きな変化がない場合は、次に説明する「漏電」などの予期せぬトラブルを疑う必要が出てきます。過去のデータと比較することで、原因の切り分けがスムーズになります。
漏電の可能性(ブレーカーが頻繁に落ちる場合は要注意)
電気をあまり使っていないはずなのに請求額が異常に高い場合は、「漏電」が起こっているかもしれません。漏電とは、本来流れるべきではない場所に電気が漏れ出してしまう現象で、これが原因で電気メーターが異常に回転し、請求額が高くなることがあります。
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 家電製品に触れたときに軽い痺れを感じる
- 壁や床が不自然に温かい箇所がある
- 焦げ臭いにおいがする
- 電気メーターが異常に速く回っている
電気代が倍になったり異常に高くなった原因

電気代の請求額が高額になる理由は、使用量の増加だけではありません。電気料金の構造そのものに変化が生じている場合や、気づかないうちにライフスタイルが変化しているケースもあります。
ここでは、電気代が高くなる主な原因を詳しく見ていきましょう。
燃料費調整額や再エネ賦課金が値上がりしている
電気料金は、使用量に基づく基本料金や従量料金だけでなく「燃料費調整額」と「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という2つの加算要素によって決まります。特に近年、電気代高騰の主な要因となっているのがこの2つです。
- 燃料費調整額
火力発電に使用する石油・石炭・LNG(液化天然ガス)の価格変動を反映したもので、原油価格や為替レートの影響を受けて毎月変動します。国際情勢の変化により燃料価格が高騰すると、使用量が同じでも電気代が大幅に上昇することがあります。 - 再エネ賦課金
全国一律で設定される料金で、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を支援するための費用です。この賦課金は毎年見直しが行われ、原則として全国一律で値上がり(もしくは値下がり)します。
電力会社が料金改定を行った
電力会社は、経営状況や燃料費の高騰などを理由に、料金改定(値上げ)を実施することがあります。
特に2022年以降、多くの電力会社が料金プランの見直しや値上げを行っており、同じ使用量でも電気代が以前より高額になっているケースが増えています。料金改定は事前に通知されますが、見落としてしまうこともあるため注意が必要です。
契約中の電気料金プランが生活スタイルに合っていない
電気料金プランには、時間帯別プラン・基本料金ゼロプラン・オール電化向けプランなど、様々な種類があります。
現在の契約プランが、ご家庭の電力使用パターンと合っていない場合、無駄な電気代を支払っている可能性があります。例えば、夜間割引プランを契約しているのに日中の電力使用が多い家庭では、割高な料金を支払うことになります。
- 日中在宅が多いか、夜間中心の生活か
- 月間の電力使用量はどれくらいか
- 契約アンペア数は適切か
- オール電化住宅かガス併用か
家電の使用量や稼働時間が増えている
気づかないうちに、家電の使用時間や頻度が増加しているケースは意外と多いです。
リモートワークの普及により在宅時間が延びた、家族が増えた、ペットを飼い始めて冷暖房を長時間使用するようになったなど、ライフスタイルの変化により電力消費が増えることがあります。
- エアコン
- 電気ヒーター
- IHクッキングヒーター
- 電気ポット
- ドライヤー
また、古い家電製品を使い続けている場合、省エネ性能が低下しており、同じ使用方法でも電力消費が増加している可能性があります。
政府の電気代補助金が終了した
2023年1月から2024年5月まで、政府による電気代の補助金制度「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が実施されていました。
出典:電気・ガス料金支援|経済産業省 資源エネルギー庁
この制度により、家庭向けの電気料金が1kWhあたり最大7円程度割引されていた時期がありましたが、補助金の終了に伴い、実質的な電気代が上昇したように感じる方も多いでしょう。これは実質的な値上げではないものの、請求額としては増えるため、値上がりの原因の一つとして認識しておく必要があります。
あなたの電気代は本当に高い?世帯別の平均額と比較

電気代が高いと感じても、実は平均的な金額だったというケースもあります。
ご自身の電気代が本当に高いのかを判断するために、世帯人数別の平均額と比較してみましょう。
1〜2人世帯の平均電気代
単身世帯や二人世帯の場合、月額平均は6,000円〜11,000円程度です。
出典: 総務省統計局「家計調査2024年 世帯人員別」
2024年の総務省「家計調査」によると、単身世帯の平均電気代は約6,756円、二人世帯では約10,878円となっています。単身世帯の場合、在宅時間の長短により電気代は大きく変動します。日中ほとんど家にいない方であれば5,000円以下に抑えることも可能ですが、在宅勤務が多い方は8,000円を超えることもあります。
二人世帯では、共働きか片方が在宅かによって使用量が変わります。夫婦共働きで日中不在が多い家庭では、夜間割引プランへの切り替えで節約効果が高まる可能性があります。
3〜4人世帯の平均電気代
三人世帯や四人世帯の場合、月額平均は12,000円〜13,000円程度です。
出典: 総務省統計局「家計調査2024年 世帯人員別」
総務省のデータでは、三人世帯が約12,651円、四人世帯が約12,805円となっています。子育て世帯の場合、子どもの年齢により電力消費パターンが変わります。小さな子どもがいる家庭では、室温管理のためにエアコンを長時間稼働させることが多く、電気代が高くなる傾向があります。
中高生がいる家庭では、スマートフォンやゲーム機の充電、勉強用の照明など、個別の電力使用が増加します。家族全員の生活リズムがバラバラな場合、各部屋で個別にエアコンや照明を使用するため、電力消費が増える傾向にあります。
季節による電気代の変動(夏・冬は1.5〜2倍に)
電気代は季節により大きく変動し、夏と冬は春秋の1.5〜2倍になることも珍しくありません。
エアコンは家庭内で最も電力を消費する家電の一つで、冷房や暖房の使用頻度が高まる7〜8月と12〜2月は電気代が跳ね上がります。特に冬季の暖房は、外気温との温度差が大きいため、冷房よりも電力消費が多くなる傾向があります。
前月と比較して電気代が高いと感じても、季節要因である可能性が高いため、前年同月との比較が重要です。
オール電化住宅の場合の平均額
オール電化住宅の電気代は、月額平均15,000円〜20,000円程度になることが一般的です。
オール電化とは、調理・給湯・暖房をすべて電気で賄う住宅のことで、ガス代がかからない代わりに電気代が高額になります。しかし、ガス代と電気代を合計した光熱費全体で比較すると、オール電化の方が安くなるケースも多くあります。
オール電化住宅では、夜間電力が割安な時間帯別プランを活用することで、給湯や蓄熱暖房のコストを削減できます。
電気代を節約する5つの方法

電気代が高いと感じたら、具体的な節約対策を実践しましょう。ここでは、今日から始められる効果的な節約方法を紹介します。
家電の無駄遣いを減らす
日常生活でのちょっとした工夫が、電気代の節約に繋がります。
使っていない部屋の照明やエアコンをこまめに消す、テレビを見ていないときは電源を切る、充電が完了したらコンセントから抜くなど、基本的な習慣を見直すだけでも効果があります。
待機電力は家庭全体の電力消費の約5%を占めており、年間で約7,000円の電気代がかかっています。使用していない家電製品のコンセントを抜くことで、年間3,000円〜3,500円程度の節約が可能です。
出典:資源エネルギー庁「平成24年度エネルギー使用合理化促進基盤整備事業(待機時消費電力調査)報告書概要」
- 電源スイッチ付きタップを活用して待機電力をカット
- 冷蔵庫の開け閉めを最小限に
- 洗濯物はまとめ洗いで回数を減らす
- 照明器具やエアコンのフィルターを清掃する
電気料金プランを比較して切り替える
電気代の「単価」を下げるのに最も効果的なのが、電力会社の乗り換えや契約プランの変更です。2016年から電力自由化が始まり、今では数多くの会社が独自の料金プランを提供しています。一人暮らし向け・家族向け・特定の時間帯が安いプラン・ガスや携帯電話とのセット割など、種類は豊富です。
まずは、現在の検針票を元に、複数の電力会社のシミュレーションサイトで料金を比較してみましょう。切り替え手続きも新しい電力会社への申し込みだけで完了し、現在の電力会社への解約連絡は不要です。電気が使えなくなる期間も発生しないため、安心して切り替えられます。
古い家電を省エネ性能の高い機種に買い替える
製造から10年以上経過した家電製品は、省エネ性能が大幅に向上した最新モデルへの買い替えを検討しましょう。
初期費用はかかりますが、長期的に見れば電気代の削減効果で元が取れることも多くあります。特に冷蔵庫・エアコン・洗濯機・テレビなどは、技術革新により省エネ性能が飛躍的に向上しています。家電公取協の「しんきゅうさん」というサイトでは、現在使用している家電と最新モデルの年間電気代を簡単に比較できます。
消費電力の多い家電の使い方を見直す
消費電力が大きい家電(エアコン・冷蔵庫・乾燥機など)の使い方を工夫するだけでも、節電効果は大きいです。
環境省によると、エアコンの場合、冷房時は室温28℃、暖房時は室温20℃を目安に設定することが推奨されています。冷房時の設定温度を1℃高くすると約13%、暖房時の設定温度を1℃低くすると約10%の節電効果があります。フィルターを2週間に一度清掃することで、冷房時で約4%、暖房時で約6%の消費電力削減が見込めます。
出典:環境省「みんなで節電アクション!家庭でできる節電アクション」
- エアコン:自動運転モードの活用、短時間外出時は連続運転
- 冷蔵庫:壁から適切な距離を保ち放熱スペースを確保
- 照明:LED電球への切り替えで約71%の節電
- 洗濯機:まとめ洗いとスピードモードの活用
契約アンペア数を下げて基本料金を減らす
契約アンペア数が実際の使用状況より大きい場合、アンペア数を下げることで基本料金を削減できます。
契約アンペア数は、家庭で同時に使用できる電気の最大量を表しており、アンペア数が大きいほど基本料金が高くなります。単身世帯なら20〜30A、二人世帯なら30〜40A、三人以上なら40〜50Aが目安です。
ただし、アンペア数を下げすぎるとブレーカーが頻繁に落ちるため、同時使用する家電の消費電力を確認した上で適切な数値を選びましょう。
契約アンペア数の変更は、電力会社に連絡するだけで無料で対応してもらえます。変更後、不便を感じたら再度変更することも可能です。
まとめ
電気代の請求がおかしいと感じたら、慌てずに原因を確認することが大切です。
- 検針票で使用量と料金単価を確認する
- 前年同月と比較して異常な増加がないかチェック
- 漏電の可能性も視野に入れる
- 燃料費調整額や料金改定の影響を確認
- 世帯別の平均額と比較して客観的に判断
- 電気料金プランを見直して最適化
- 家電の使い方を改善し無駄を削減
電気代の節約は、一度実施して終わりではなく、継続することが重要です。小さな工夫の積み重ねが、年間で見ると大きな節約につながります。できることから少しずつ取り入れて、無理なく電気代を削減しましょう。
電力会社の乗り換えやアンペア変更は少し手間かもしれませんが、一度見直せば継続的に家計を助けてくれる対策です。この機会に、ご家庭の電気の使い方と契約を見直してみてはいかがでしょうか?